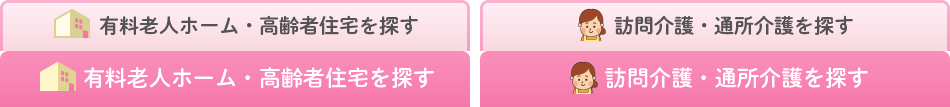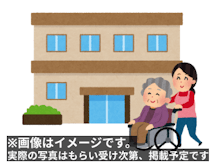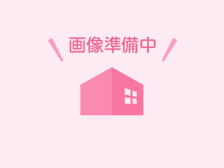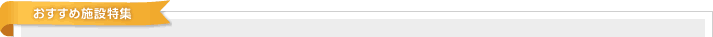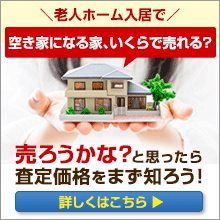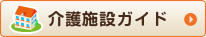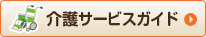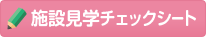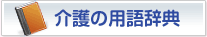【詳解】有料老人ホームとは?意外と知らない種類の違い | 正しい選び方は?
不安や悩みの種類は違えど、誰もが気になる老後の暮らし。
親や家族には安心して老後を過ごしてほしい、もちろん、自分も充実した老後を過ごしたいと思いますよね。
そんな時に選択肢の1つとして浮かぶのが、有料老人ホームでの快適な生活ではないでしょうか。
「老後は有料老人ホームでゆったり過ごしたいな……」
「離れて暮らす親が心配。近くに良い有料老人ホームがあれば入居させたい」
そんなことを考えている方も少なくないはず。
でも、ちょっと待ってください。そもそも、有料老人ホームってどんな施設か知っていますか?
試しにネットや本で調べてみると、次から次へと出てくる聞きなれない言葉。介護付に住宅型、サ高住。入居基準に権利形態、特定施設。
思った以上にわからないことが多く、「???」となってしまった方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そんな方のために有料老人ホームの定義・基準から選び方、色々ある種類との違いなど、分かりやすく解説していきます。

目次
有料老人ホームの定義
まずは、有料老人ホームが、法律上どのように定義されているか確認しておきましょう。
老人福祉法によると、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は介護等の供与をする事業を行う施設」という定義になっています。
・・・わかりませんよね。
言い方を変えてみると「食事、介護、家事、健康管理、どれかのサービスを提供する高齢者向けの居住型(泊まれる)施設」となりますが、まだ漠然としていますね。
まず一番最初に知っておきたいのは、有料老人ホームには4つの分類があり、必ずどれかに該当する、ということです。
「有料老人ホームって1種類じゃなかったの?」
そうなんです。もう自分や親・家族のために有料老人ホーム探しを始めている方はおわかりだと思いますが、実はいくつか種類があります。
選び方や、入居の決め手について解説する前に、まず有料老人ホームの種類や特徴を紹介します。介護施設として、よく聞く「特養」や「老健」「グループホーム」との違いもあわせて紹介しますね。
有料老人ホームは4種類
主に次の6種類が「有料老人ホーム」と呼ばれています。
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム・特定施設入居者生活介護の指定がないサ高住
介護付有料老人ホーム
行政から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホームです。
特定施設入居者生活介護とは、施設が提供する介護サービスのこと。介護付有料老人ホーム(以下、介護付)では、掃除や洗濯などの生活支援サービスから入浴介助などの介護サービスまでを、施設の介護職員が提供しています。
多くの方が思い描く老人ホームのイメージにいちばん近いタイプかもしれませんね。
ちなみに、特定施設入居者生活介護の指定を受けるには、一定の基準を満たさなければいけません。
例えば、原則個室、介護職員・看護職員合わせて人員配置3:1以上、生活相談員・機能訓練指導員・計画作成担当者・管理者の人数など、こと細かに規定されています。
住宅型有料老人ホーム
掃除や洗濯といった生活支援等のサービスを提供する有料老人ホームです。
介護付と住宅型有料老人ホーム(以下、住宅型)の違いは、施設の職員が介護サービスを提供しているかどうかという点です。
住宅型で介護が必要な場合は、外部の介護サービスを利用します。
「え?施設で介護を受けられないの?」と思うかもしれませんが、お部屋で、訪問介護等の外部業者の介護サービスを受ける形となります。また、居宅介護支援(ケアマネジャー)やデイサービスを併設している施設も多く、その場合は介護付とほぼ同じ環境となります。
職員配置の基準も介護付とは大きく異なり、管理者以外の職種(介護職員、看護職員、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者)については任意配置。施設ごとに提供されるサービスが異なり、介護付と同等の基準をクリアしている施設もあれば、介護度が高くなると退去しなくてはならない施設もあります。
健康型有料老人ホーム
食事等のサービスを提供する有料老人ホームで、介護付・住宅型と大きく違っている点は、介護サービスが必要になると退去しなくてはならないこと。
2018年12月現在、その数は全国でわずか10施設程度。今後増加することも考えづらく、本記事ではこの項目以外では取り扱いません。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)は、高齢者向けの賃貸住宅のこと。高齢者にふさわしい住環境(規模・設備)と、安否確認・生活相談サービスの提供が義務付けられており、「サ高住(さこうじゅう)」「サ付き(さつき)」と呼ばれることもあります。
介護付との大きな違いは部屋の広さ。原則25㎡以上と、居室が広く作られています。職員については、安否確認・生活相談を行う人員がいれば良く、介護職員などその他の人員に関する基準はありません。
居宅介護支援やデイサービスを併設していることも多く、また食事提供や清掃を行っていることから、実際は、その多くが有料老人ホームに該当しています。さらに、特定施設入居者生活介護の指定を受けた「サービス付き高齢者向け住宅かつ介護付有料老人ホーム」もあります。
いかがですか?
有料老人ホームとひと口に言っても、その種類はさまざまで区別が難しいですね。介護付・住宅型・サ高住の特徴を簡単に比べてみると、次のようになります。
介護付有料老人ホーム
要介護の入居者が多く、介護度が高くなっても最期まで施設に住み続けられるのがメリット。介護サービスは施設の介護職員が提供し、看護職員による医療処置が可能な施設もある。
住宅型有料老人ホーム・特定施設入居者生活介護の指定がないサ高住
自立・要支援の入居者が多く、介護サービスを提供する事業者を自由に選択・変更できるのがメリット。暮らしの自由度も比較的高い。ただし、介護度が高くなると退去しなくてはならないことがある。
有料老人ホーム選びは種類から!特養・老健・グループホームとの違い
続いて、その他施設について見ていきます。
老人ホームについて調べていると、「特養(とくよう)」「老健(ろうけん)」「グループホーム」といった言葉を耳にすることはありませんか。
いずれの施設も有料老人ホームとは似て非なるもの。その違いをしっかり確認していきます。
「特養」とはどう違う?
特養(とくよう)は、特別養護老人ホーム・介護老人福祉施設の略称です。地方公共団体や社会福祉法人が運営する介護施設で、原則、要介護3以上の方しか入居することができません。
居室面積は10.65㎡以上、介護職員・看護職員の人員配置は介護付と同じ3:1以上などの基準があり、利用料の安さが最大のメリット。最近増えている個室タイプの特養は利用料が高くなるものの、生活保護や年金の範囲で入居できる施設も数多くあります。
ただ、安価な特養には入居希望者が殺到し、エリアによっては長期間入居待ちとなっているのが実状。一方で、(前述の通り、利用料が高くなるため)料金は高くなりますが、介護にかかわる職員の体制や自由度の高さ、設備やサービスの充実度から有料老人ホームを選ばれる方が多くいらっしゃいます。
「老健」とはどう違う?
老健(ろうけん)は、介護老人保健施設の略称です。原則、要介護の認定を受けている方しか入居することができません。有料老人ホーム・特養と同じく介護サービスを受けることはできますが、高齢者の在宅復帰を大きな目的としているため、機能訓練やリハビリテーションがサービスの中心です。
有料老人ホーム・特養との大きな違いは、一定期間で退去しなくてはならないこと。在宅復帰を前提としているためで、“終の棲家”とするのは難しいでしょう。
「グループホーム」とはどう違う?
認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症の方を対象としています。介護保険サービスの中では、地域密着型サービスに該当し、原則、その地域に住む要支援2または要介護認定を受けている方しか入居できません。
5~9名を1ユニットとしてユニットごとに共同生活をおくりますが、設置できるのは最大3ユニット(最大入居者数27名)までと小規模の施設です。
地域における認知症ケアの拠点で、有料老人ホームと比較すると費用は安価なことが多いです。ただし、医療対応や看取りを行っていないところが多く、医療処置が必要な状態になると退去しなくてはならない場合があります。
ここまでの解説で、各種有料老人ホームとその他の施設、どれも似ているようでありながら、それぞれに特徴があることがお分かりいただけたでしょうか。
各施設の特徴や違いを把握し、入居する方の状態に合った施設を探しましょう。
どんな施設が自分には向いているのか?

施設の種類について説明したところで「いよいよ施設探し」と進みたいところですが、各施設の特徴や違いについて「すっきり理解できた」という方もいれば、「いや、まだまだ複雑で分かりづらいな」という方もいるでしょう。
そこで、最初の一歩として、自分や家族の現状に合う施設選びの参考パターンをまとめてみました。
ざっくりパターン別おすすめ施設例
有料老人ホーム、その他の施設にかかわらず、各種パターンに分けておすすめの施設種類を紹介すると、以下のようになります。
今は自立しているが、1人での生活が不安。いずれは特養などの施設に入居しようと思っている人
生活の自由度が高い住宅型・サ高住がおすすめ。
今は自立しているが、将来を考えて最期まで過ごせる施設に入居したい人
住宅型・サ高住にも条件に合う施設はあるが、最期まで利用したいなら介護付がおすすめ。
要介護認定を受け、在宅生活が難しいと感じている人
介護体制の手厚い住宅型・サ高住など条件に合う施設はあるが、特養もしくは介護付がおすすめ。
病院から退院するが、医療対応が必要で、在宅生活が難しいと感じている人
医療対応が必要な場合は、看護職員常駐の施設を選ぶ必要があるため、特養もしくは介護付がおすすめ。
リハビリを行い、在宅復帰を目指す人
リハビリの充実した老健がおすすめ。
認知症を患っている人
介護体制の手厚い住宅型・サ高住など条件に合う施設はあるが、特養、介護付、グループホームがおすすめ。
重要なのは「いつから、いつまで」入居できるか
パターンごとの施設種類からおわかりの方もいるかもしれませんが、「いつから入居するか」「いつまで入居するか」の2つのタイミングが施設選びでは非常に重要になります。いつから入居していつまで過ごすのか、用意できる資金との兼ね合いも含め、以下のように具体的にイメージしておくとよいでしょう。
いつから入居する?
- 将来に備えて元気なうちに施設に入居したい
- 70歳になったら入居、要介護になったら入居など、あらかじめタイミングを決めておく
- 資金面から入居はできるだけ先にしたい。在宅介護が厳しくなってから検討する
いつまで入居する?
- 入居した施設で最期を迎えたい
- 自宅で最期を迎えたい
- 要介護になったら専門的な施設へ移りたい
- 要介護や認知症になっても同じ施設で過ごしたい
有料老人ホーム探しの3つのステップ
これまで、有料老人ホームの種類の選び方を中心に説明してきましたが、同じ種類でも、施設ごとに個性があるのが有料老人ホームの特徴。
次は、その個性豊かな有料老人ホームの中から、自分や家族に合った施設を探す方法を3ステップに分け、解説していきます。
- 判断基準を把握する
- 優先順位・妥協点を決める
- 必要な情報を集める
その1:判断基準を把握しておく
次のステップでは、入居される方が大事にしたいポイントを明確にしていきます。
施設を選ぶ時に、最も気になる点は介護体制に医療体制?それとも食事や設備でしょうか?
判断基準となる8つのポイントをご紹介しますので、自分や家族にとって「ここは大事にしたい!」と思うポイントを考えながら、読み進めてみてください。
①入居基準
多くの有料老人ホームでは、入居に際して、主に以下のような基準が設けられています。基準を把握し、入居が制限される可能性がある方は、認識しておきましょう。
要介護度
住宅型・サ高住は施設によって、要介護度の高い方は入居できないことがあります。介護付は要介護度が高くても入居できます。
認知症
住宅型・サ高住は施設によって、認知症の方は入居できないことがあります。介護付は入居可能ですが、徘徊・自傷行為・暴力など重度の認知症の方は入居できないことがあります。
医療体制
住宅型・サ高住は、医療的ケアを必要とする方は入居できないことがあります。介護付は入居可能な施設が多いですが、医療行為の内容によっては入居できないことがあります。
身元保証人・連帯保証人
施設によって違いがあり、身元保証人・連帯保証人が居ないと入居できないことがあります。
②費用
支払能力に応じた施設を選ぶことが大切です。
基本的な費用体系は「入居一時金+月額利用料」となっており、一時金は入居時にいくらかが初期償却されます。月額利用料の内訳は主に水道光熱費や介護サービス費(介護保険適用)、上乗せ介護費、おやつ代、レクレーション費、洗濯代などとなります。
金額の高い低いは、立地や設備、職員体制に左右されることが多く、職員数が多い施設や東京都23区内の施設、新しい施設などは金額が高め。
年金や生活保護の範囲内で入居できる施設はあるものの、ごく少数です。
あくまで参考ですが、有料老人ホームとサ高住の平均的な利用料金総額は、有料老人ホームで約19万円(一時金は月額に換算して追加)、サ高住で約14万円となっています。
③介護体制
介護の手厚さを測る上で、「3:1以上」や「2.5:1以上」などと記載されている職員体制が目安の1つです。
3よりは2.5、2.5よりは2と、数字が少ないほど「1人あたりの介護・看護職員の数が多い」ということになります。ただし、介護体制が充実すればするほど、「上乗せ介護費」として利用料が高くなることがあるので注意しましょう。
また、この数字があくまで目安であることにも注意しましょう。介護体制は職員の勤務状況で変動することが多く、「3:1以上」の施設が「2.5:1以上」の施設より介護の質が低いということは決してありません。
配置人数にこだわり過ぎず、専門資格保有者の数、要介護度の上昇や認知症に対応できるかなどを、見学や体験入居で確認するとよいでしょう。最期まで住み続けることを考えた場合、重要な項目となります。
④雰囲気
有料老人ホームは、レクリエーションなどで他の入居者と交流する機会が多く、施設の雰囲気も重要なポイントになります。
周囲の土地柄、自分の趣味を活かせるサークルの有無、職員や他の入居者の雰囲気、施設長の考えなどを参考にしましょう。
見学すれば直接話を聞くことができ、雰囲気も実感できます。
⑤立地・アクセス・周辺環境
アクティブなシニアの方や家族にとっては、重要なポイントではないでしょうか。
都心で賑やかな雰囲気がよいのか、郊外で落ち着いた雰囲気がよいのか、住みやすい環境は人それぞれです。また、気軽に外出を楽しみたいなら、商業施設や公園の有無といった周辺環境や、都心部からのアクセスをチェックしておきましょう。アクセスの良さは、家族の訪問しやすさにもつながります。
⑥家族とのかかわり
「自宅と変わりなく家族と会うことができるか」を重視する場合は、面会時間や家族の宿泊の可否、運営懇談会の実施回数、家族が参加可能なイベントの実施回数などから判断するとよいでしょう。オリジナルの新聞を発行したり、職員がこまめに報告してくれたり、施設ごとにさまざまな取り組みが行われています。
⑦食事
食事にこだわる方は多く、施設選びの重要なポイントになります。住宅型・サ高住では食事を提供していないこともあり、しっかりチェックしたいところ。
調理の場所(施設内の厨房か外部委託か)、セレクト食や行事食・イベント食の有無とその費用、形態食や治療食への対応などから判断しましょう。見学時に試食が可能なら、試してみることを強くおすすめします。
⑧建物・設備
機能性を重視した施設から、ホテルのような豪華な施設まで千差万別です。屋上の庭園でガーデニングができたり、家族も利用できる温泉があったり、ビリヤード台や麻雀台が用意されている施設もあります。建物や設備は、見学や体験入居で確認するのが一番です。
その2:優先順位を決めて、妥協するポイントを決めておく
入居される方の判断基準が明確になれば、自ずとその優先順位も見えてくるはずです。
判断基準の設定例
優先度の高い項目を
- 要介護2、軽度の認知症の入居が可能
- 費用は月額20万円以下
- 介護体制あり
- 食事内容が充実している
優先度の低い項目として
- 面会に行かれる家族の自宅から1時間くらいのアクセス
- できれば新しい施設が良い
見学等で確認する項目として
- 施設の中の雰囲気が良い、明るい
- 利用する設備が新しい、多い
自治体などの相談窓口や公的サイト、入居紹介サービスなどを上手く利用して多くの情報を集めても、比較するポイントが曖昧では自分や家族に合った施設を見つけることはできません。重視するポイントに優先順位をつけておくことで、施設を絞り込みやすくなります。
100%満足する施設を見つけるのは難しく、時には妥協も必要です。納得いく妥協のためにも、優先順位はしっかりつけておきましょう。
その3:必要な情報を集める
良い施設を探すためには、より多くの情報が必要。では、その情報はどこで手に入るのでしょうか。
実は結構難しい老人ホーム探し
実は、情報収集の段階で壁にぶつかってしまうことが多くあります。それは次の2点が理由と言われています。
理由1:全種類の施設情報を網羅している公式サイトがない
厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」に掲載されているのは、特定施設(介護付)のみ。住宅型を探そうと思うと、市区町村が独自にまとめたページを見なければいけません。また、サ高住は別に「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」が存在しています。
このように全種類の施設を一元的に見ることができず、比較しづらいのが難点です。
理由2:金額、設備、サービス内容など施設の特徴が豊富すぎる
金額だけをみても、年金内で暮らせるものから入居金数千万円のものまであり、支払方式もさまざま。さらに、設備やサービスまで調べ始めると何が良いのか分からなくなります。
効率的に情報収集する3つの方法
情報収集の方法は主に3つありますが、どの方法で探すにしても施設の数は膨大。自分なりの判断軸や優先項目を決めておくことで、必要な情報をスムーズに集めることができます。
①自治体や地域の相談窓口で教えてもらう
地域包括支援センター、区役所等の福祉課や介護保険課、地域の福祉相談窓口に教えてもらう。
②行政のWebサイトを利用する
行政が運営する「介護サービス情報公表システム」「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を活用する。
③入居紹介サービス
入居紹介サービスは基本的に無料で利用できます。インターネットで簡単に検索でき、気軽に相談できるものや居住地域に特化したものまで特色もさまざま。ただし、運営会社が提携している有料老人ホームのみ紹介され、情報が偏ってしまうのがデメリット。
良い有料老人ホームを見つけた!ここからどうする?

「良い有料老人ホームがネットで見つかった!すぐにでも申し込みたい!」
ちょっと待ってください!確かにネットには色々な有料老人ホームの情報がのっていますが、百聞は一見に如かず 、です。
もちろん迷いすぎても良くありませんが、複数の施設を比較し、見学や体験入居を行うことは、ご自身の入居後の納得感にも繋がります。入居される方の納得のいく施設選びができるよう、情報収集から入居までの流れをみていきましょう。
入居する施設はこう決める ~情報収集から見学まで~
良さそうな施設が見つかった際には、施設見学にも参加し、複数施設を比較検討していきましょう。
資料請求も情報収集の1つの手段
最近は、公式サイトや仲介サイトに多くの情報が掲載されていますが、資料請求も立派な情報収集の1つ。資料から暮らしの様子が分かることもあります。資料請求のついでに、不明点や疑問点を直接施設へ聞いてみてもいいですね。
気になった施設は空室確認を!
Webサイトや資料から情報を集めても、空室がなければどうしようもありません。気になった施設があれば、すぐに空室確認して見学に出かけましょう。
いざ見学へ!ここがポイント
見学は事前予約する、これがしっかりと施設を見学する秘訣です。訪問する時間帯によっては、試食ができたり、レクリエーションを見学できたり、実際の生活を感じることができます。試食は有料の場合もあるので、予約時にしっかり確認しましょう。
また、気になることや聞きたいことをまとめておくと、スムーズに話が進みます。当日はメモを忘れずに持参してくださいね。
見学時に確認しておきたいポイント
- 施設や職員の雰囲気
- イベントやレクリエーション
- 食事(試食や献立表など)
- 医療行為について
- 月額利用料に含まれる費用は何か
- 周辺環境
入居の流れ
「見学して満足できる施設が見つかった」となれば、いよいよ入居です。どのような手続きが必要なのでしょうか。
一般的な入居までの流れ
施設によって多少の違いはありますが、次のような流れが一般的です。
見学して施設決定
↓
入居する居室を選択
↓
入居申込み(仮押さえに費用が必要な場合があります。)
↓
契約手続き(一般的にはこの時点で入居一時金を支払います。)
↓
引っ越し・入居
入居までの期間はどのくらい?
施設選びから入居までは、皆さんが思っている以上に時間がかかる場合があります。余裕のあるスケジュールを立てるに越したことはありませんが、急きょ入居が必要となるケースも多いですよね。
施設側もその点は理解しており、短期間での入居に対応してくれることもあります。また、引っ越しを手伝ってくれる施設もあるので、まずは相談するのが良いでしょう。
入居手続きは何が必要?
重要事項説明書の説明を受け、入居契約書や健康診断書などの必要書類を提出します。契約には、身分証明書や印鑑、介護保険被保険者証などが必要ですが、この時点で入居一時金の一部もしくは全額の支払いが必要なケースもあります。
少しでも不明な点があれば、納得できるまで施設に確認することが大切です。
権利形態と支払い方式について
居住の際の権利形態と支払い方式は、契約内容にも関わる重要な項目。ここで確認しておきましょう。
権利形態
利用権方式:施設へ居住する権利と介護等のサービスを利用する権利が一体になっている
賃貸借方式:一般的な賃貸借契約と同様で、介護等のサービスは契約に含まない。入居者が死亡しても権利は相続される
終身建物賃貸借方式:賃貸借方式と同じだが、入居者が死亡した時点で権利は消滅する
支払い方式
全額前払い方式:終身利用した場合の家賃やサービス費用の全部を入居一時金として一括して支払う方式
一部前払い・一部月払い方式:終身利用した場合の家賃やサービス費用の一部を入居一時金として支払い、その他は月払いする方式
月払い方式:入居一時金はなく、家賃やサービス費用を月払いする方式
選択方式:全額前払い方式、一部前払い・一部月払い方式、月払い方式のいずれかを入居者が選択できる
体験入居で最終チェック
ほとんどの施設が体験入居を実施しており、そのまま本入居する人も少なくありません。体験入居では、職員の雰囲気や入居者の様子、サービスの充実度や設備の使いやすさなど、見学だけでは分からない部分を確認することができるので、最終チェックとしてぜひ利用してください。
ショートステイを行っている施設もありますが、本入居を前提としていない点や介護保険が適用される点が体験入居と異なります。
有料老人ホームではどんな生活を送るの?

さて、ここまで探し方や入居までの流れについて解説してきましたが、入居後の暮らしはイメージできていますか?
冒頭でも記載したとおり、有料老人ホームに「こういう生活をしなさい」という基準はありません。施設として食事や入浴の時間帯などを設定していますが、それ以外は皆さんが自由に過ごし、レクリエーションやイベントには希望する方が参加します。
ここからは、一般的な有料老人ホームでの暮らしがどういうものかを、具体的に紹介していきます。
一日の流れ
一般的な有料老人ホームでは以下のようにスケジュールが設定されています。
| 起床 | |
|---|---|
| 朝食 | |
| レクリエーションや機能訓練など | |
| 昼食 | |
| 外出や入浴、イベントなど | |
| 夕食 | |
| 就寝 |
レクリエーションや行事・イベント、機能訓練、ティータイムなど、入居者が退屈することのないよう工夫を凝らしています。起床時刻や就寝時刻は決められていないこともありますが、基本的に規則正しい生活を送ることができるように施設が決めています。
どんなサービスが受けられるの?
有料老人ホームではどのようなサービスが提供されているのでしょうか。一例として、介護付で提供される主なサービスをご紹介します。
※住宅型・サ高住の場合は、訪問介護やデイサービスを別途依頼することで同等のサービスを受けることができます。
介護サービス
介護保険を利用して以下のような介護サービスを受けることができます。
- 食事介助
- 排泄介助
- トイレ誘導
- 服薬介助
- 入浴介助
- 口腔ケア
- 移乗介助
- 機能訓練
- おむつ交換
- 体位交換
- 夜間の見回り
- 整容
生活サービス
日常生活のサポートとして、以下のようなサービスを受けることができます。
- 生活相談
- 買い物代行
- 居室清掃
- 洗濯
その他独自に実施されているサービス
独自に以下のようなサービスを提供している施設もあります。気になるサービスがあれば、提供の有無について施設へ確認しましょう。
- 理美容
- 役所手続き代行
- 金銭・貯金管理"
健康管理体制
介護付の場合、「協力医療機関」を定めて協力契約を結んでおくことが運営基準の1つとなっており、協力医療機関が訪問による健康相談・健康診断などを定期的に行われています。
働いている人の資格って?
有料老人ホームには、介護福祉士や介護支援専門員、看護師など、さまざまな資格を持つ職員が働いています。
ところが、意外にも有料老人ホームでは資格がないと働けないというわけではありません。
介護職の入門資格と言われる介護職員初任者研修の取得を支援している施設もありますが、実際、有料老人ホームには無資格の職員が少なからずいます。
入居する立場なら「お世話をしてくれる職員は介護のプロであってほしい」と誰もが思うところですが、職員の資格の有無や資格保有者の割合はあくまで参考。職員同士の雰囲気やコミュニケーションの取り方、運営会社の研修体制、施設の目標や方向性などから、サービスの質を判断しましょう。
食事
毎日の食事をはじめ、おやつや行事食・イベント食など、入居者にとって大きな楽しみである食事に力を入れている施設は多く、栄養士を配置したり、形態食や治療食の対応が柔軟だったり、施設ごとの特色も豊かです。おやつや行事食・イベント食などを提供している場合は、毎月の食費とは別に費用が徴収されることがあります。
調理する場所にも違いがあり、施設内の厨房で調理している場合と外部で調理している場合があります。
入浴
介護付の場合、基本的な入浴回数は週2回、多いところで週3回です。住宅型・サ高住の場合は特に入浴回数は決まっておらず、好きな時に入ることができます。
大浴場やひのき風呂、介護浴室などの入浴設備が充実していたり、「ゆず湯」や「しょうぶ湯」など季節感を大切にしていたり、施設ごとのこだわりもさまざま。中には天然温泉に入れる施設もあります。入浴回数や入浴設備など、気になる人は確認しておくといいですね。
イベント
正月・節分・ひな祭り・お花見・納涼会・紅葉狩り・クリスマス会などの年間行事のほか、誕生日会が毎月の定番イベントとなっています。
また、地域交流が盛んな施設では、慰問演奏や近隣の小中学校の職場体験、近隣・系列の保育園・幼稚園との交流が行われています。
レクリエーション
介護付、住宅型、サ高住では日常生活の中にレクリエーションが組み込まれています。日常的に行われるレクリエーションは、入居者の心身の活性化や身体機能の維持・向上、入居者同士のコミュニケーションなどを目的としています。
集団で行うレクリエーションとして代表的なものは、風船運び・クイズ・脳トレ・カラオケなど。個別に行うレクリエーションでは、習字・折り紙・編み物など。その他にサークル活動として、囲碁や将棋、ビリヤード、麻雀など、趣味の合う者同士が集まる機会が提供されています。
お酒・タバコについては施設ごとに方針が異なる
認められている施設でも、周囲の方への配慮から飲酒・喫煙場所が決められていることがほとんど。飲酒に関しては、居室のみ可能としている場合もあれば、逆に居室内での事故を避けるため食堂に限定している施設もあります。
外出・外泊って自由にしていいの?
住宅型・サ高住は、外出・外泊ともに基本的に自由です。ただし、大まかな予定や外出先・外泊先などについて、確認を行う施設があります。
介護付の場合は、家族の許可が必要な施設が多いので、基本的には家族の同伴かスタッフの付き添いが必要となるでしょう。
家族の面会時間って決まっているの?
面会時間は施設によって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。24時間面会可能なところもありますが、防犯上の理由から夜間は施錠していることが多く、そのような施設では、夜間・早朝の訪問は事前連絡が必要となります。
ほかにも、家族と交流する機会が設けられています。状況報告や情報交換を行う運営懇談会を年1~2回開催しているほか、館内報の発行や電話連絡の義務化など独自の取り組みも盛んです。また、施設で行われるクリスマス会などの行事のほとんどは、家族も参加可能となっています。
共用スペースや居室などの居住空間はどうなっているの?
施設の種類だけでなく施設ごとに違いがありますので、ここでは一般的な居住空間について紹介します。
居室タイプ
現在の主流は完全個室です。夫婦部屋を用意しているところはあるものの、他人同士が1部屋で生活する多床室は少なくなっています。何が持ち込めるの?
生活に必要な家具などは一通りそろっており、着替えさえあれば十分です。
とは言え、高齢者にとって生活環境が大きく変わる不安やストレスは相当なもの。精神的な負担を減らすため、愛用していた家具などの持ち込みを認めている施設もあります。
入居者の安全確保のため、刃物や火気は持ち込み禁止であることが多く、仏壇等もライト式が主流です。現金については、金銭管理のサービスが用意されていたり、持ち込み禁止で必要時は施設が立て替えたり、施設によって取り扱いが異なります。
判断に迷う物があれば、施設に相談するとよいでしょう。
設備
食堂、浴室、トイレ、洗面設備、医務室または健康管理室、看護・介護職員室、機能訓練室、談話室または応接室、汚物処理室、健康・生きがい施設などが一般的な設備です。
機械浴・寝台浴などの介護浴室、家族の宿泊できる部屋、地域交流スペースなど、独自に備えている施設もあります。
施設によってあるこだわりの設備
有料老人ホームのなかには、設置基準で決められたもの以外に独自の設備を備えているところがたくさんあります。その施設のこだわりが設備に表れているので、そこに着目してみるのも面白いですよ。
例えば、レクリエーションに特化したシアタールームやカラオケルーム、園芸活動ができる花壇・庭園・農園、身体を動かす習慣が身に付くフィットネスルーム、美味しい食事にこだわったレストラン、日常の癒しになる天然温泉やバーなど…。
「いいな」と思った施設のこだわりを、設備から読み取るのも施設探しのコツかもしれません。
医療体制はどのようになっているの?

ここまで選び方から、生活まで解説してきましたが、持病をお持ちの方は、医療体制も気になるところでしょう。
有料老人ホームでの医療行為は基本的に看護職員が行っており、医療体制を見極めるポイントは次の2点です。
- 看護職員が常駐しているか
- 常駐している場合、日中のみか24時間か
また、医療行為の中でも、喀痰吸引・経管栄養については、専門の研修を受講した介護職員は行うことができます。施設がそういった登録を行っているかも確認しておくとよいでしょう。
夜間の体制・オンコール体制
夜間や緊急時の体制は最も気になるところ。
介護保険法上は「1人でも要介護者である利用者がいる場合は、常に介護職員が1人以上確保されていることが必要である」と、最低1人いればよいことになっています。
実際には、多くの施設が夜間の職員シフトを工夫して1人以上で対応しているほか、24時間体制で協力医療機関や施設の看護職員が対応する「オンコール体制」を整えている施設もあります。医療面で不安を抱えた入居者の急変や、夜間の体調不良時などに用いられるなど、「オンコール体制」は入居者にとって大きな安心材料です。
どういう医療行為が可能なの?
施設で対応できる医療処置については、公式サイトなどに掲載されています。胃ろうやインスリン注射、IVH(中心静脈栄養)などが挙げられますが、施設に常駐する看護職員の勤務体制や経験によるところが大きく、正確に知りたい場合は施設へ直接問い合わせるのが一番です。
協力医療機関
協力医療機関は、有料老人ホームの医療体制に欠かせない存在です。
主な役割は往診やオンコール対応になりますが、緊急時対応については規定がなく、救急搬送で対応しているところも少なくありません。救急対応できる医療機関が施設に併設されていることもあります。
往診の体制
協力医療機関の多くは定期的に往診を行い、入居者の健康管理や健康相談を行っています。往診の頻度はそれぞれですが、内科の往診や歯科医師による口腔ケアが月1回程度行われるのが一般的。心療内科などの専門医が訪問している施設もあります。
緊急時
看護職員が対応したり、救急搬送したりと施設によってさまざまです。居室内や共用スペースにナースコールは設置されているか、医療機関との提携はスムーズか、看護職員不在時の体制はどうなっているのか、また、家族対応についても確認しておきましょう。
看取り時
介護施設での看取りケアとは、余命が残り少なくなった入居者に対して適切な終末期の看護・介護を提供することです。
近年は、「看取り介護加算」を算定して看取りの体制を整えている施設が増えています。
かかりつけ医の継続
「入居後も、前から通っていた病院で診てもらいたい」そう考える人も多いと思います。
有料老人ホームには提携している医療機関があり、入居と同時に主治医を変更する方が多いですが、かかりつけ医を変更しないことも可能です。ただし、提携している医療機関以外の病院までの送迎や付き添いサービスを実施していない場合があるので、施設に確認しましょう。
リハビリ・機能訓練は受けられるの?
生活リハビリや体操などの簡単な機能訓練については、どの有料老人ホームでも随時実施していますが、医師の指示に基づいて理学療法士や作業療法士などが行う本格的なリハビリは施設によります。リハビリ提供の有無、頻度や料金などは各施設に問い合わせましょう。
また、訪問マッサージなどの外部サービスを健康保険で利用できる施設もあります。
よくある悩み
ここでは有料老人ホームにまつわる「よくある悩み」にお答えしていきます。
虐待を行う老人ホームを見抜く方法はあるの?
昨今、虐待に関する多くのニュースがあり、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
施設側も、定期的な研修の実施や本社社員による面談など、虐待防止を積極的に取り組んでいますが、虐待が起きるかどうかはわかりません。残念ながら虐待が起きるかどうかを100%見抜く方法はありませんので、少しでも「おかしい」と感じた時は、すぐに相談することが大切。
施設の苦情相談窓口(設置義務があり、必ず設けられています)や、自治体・国保連・地域包括支援センターなどの相談窓口を利用しましょう。
入院している期間の家賃やその他費用の負担はどうなるの?
基本的に入居を継続することが可能です。
ただし、入院期間中も食費等の費用を除いた月額利用料を支払う必要があります。
まとめ
有料老人ホームに関する制度は複雑で、必要な知識がなければ満足のいく有料老人ホーム探しはできません。本記事を参考に、自分なりの判断軸と優先順位をもって、自分や家族に合う施設を探してみてください。
また、「かいごDB」では、無料で有料老人ホームの入居紹介を行っています。困った時や迷った時は、ぜひご相談ください!
監修者

大久保 典慶
介護福祉経営士1級
かいごDBの編集担当。老人ホーム等の介護・福祉・高齢者事業を幅広く運営する社会福祉法人での経験を経て、株式会社エス・エム・エスに入社。老人ホームをお探しの方やご家族に、介護・福祉に関わる情報をわかりやすくお届けします。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[かいごDB]kaigodb.com](/img/nav/head_logo.gif)